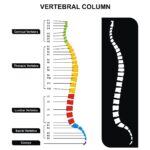therapy-theory

土屋の思考過程を話します(その1)〜細かいリリースをするな!?〜
2019.01.27
インフルエンザが流行っている。
6歳の息子も一昨日、保育園からの連絡で感染が判明・・・
なぜ、インフルエンザ感染の兆候があった息子の変化に気づかなかったか?
あまりプライベートをださないメルマガ方針なんですが、愚痴を聞いてください(スイマセン)
共働きをしている夫婦の朝はバタバタととにかく忙しい。
いつものように4歳と6歳の子ども2人をたたき起こし(どんどんプライベートが明かされていく~)、
顔を洗い、服を着替え、保育園の準備を…と尻を叩きながら
時に優しく、時に鬼のように厳しく、誘導していく。
土屋家は小さくても「自分のことは自分でやるルール」があるので、
まだ幼い子どもでも、身の回りの大抵のことは自分でやるように教育している。
この日はなぜか長男がのろく、「抱っこ~」と甘えてきていた。
DAZNでサッカーでも観たい(そう、サッカー好きなのだ)のかと思ったので無視した。
食事を摂らせ、保育園に送り届け仕事に向かった。
・・・
お昼に保育園から連絡!
そして【インフルエンザA型】に感染が判明!!!
たしかに、
朝食時に食べずに「ママ~、抱っこ~」とまた甘えてきた。
わたしはてっきり駄々をこねているのだと思ったが、兆候はあったのだ。
わたしはすっかり反省した。
言葉足らずの長男はSOSを発していたが、わたしは気がつきませんでした。
兆候はあっても気がつくとは限らない
投資をする人の多くが目をとおす日経新聞だが、同じ情報を意味ある情報として読み取っている人はごく僅かだ。
馬の知識があって、出走前のパドックで馬の状態をみても、実際のレースを当てられる人も僅か。
臨床に目を向けたときに
あなたの前で患者さんが既に何らかの兆候を示しているにも関わらず、
あなたは気がついていないことはないだろうか?
そんな話しを今日は紹介したい。
変だぞ、この肩?
ケーススタディという思考を鍛えるオランダ徒手独特の雰囲気を感じてもらいたいので、
その思考過程も言葉にしてみた。
クリニカルリーズニング(臨床推論)ともいいます。
<ケース>
趣味)アメフト
主訴)右肩三角筋後方の痛み
ちなみにその3ヶ月前に左肩腱板の再腱術を受けてリハビリ最終フェーズ
馴染みのそのお客さんは学生の頃からアメフトで活躍。
40代となった現在でもシニアリーグで結構本気でプレーを続けている。
昔から背の割に肩が異様に大きく、
見た目、それはパッドを入れているぐらいぱんぱんに張っている感じ。
もの凄い筋トレをやり続けてきていたから、その影響だとばかり思っていました。
実は昨秋、左肩の腱板損傷で手術をして、それ以来、好きなアメフトを一時的に休み、
トレーニングよりも手術後のケアとリハビリに励むように。
つまり同じように肩を鍛えることはなくなった。その結果、左肩は一般の人と同じような三角筋に戻ったけれど、相変わらず、右肩は大きく張ったままだった。
おかしい?
なぜ、運動負荷がトレーニングストップしたにも関わらず、右肩は萎縮しないのだろう???
<仮説> ~思考過程①~
ここで考えていたことは、
硬いが弾力性がある三角筋の触診結果を踏まえ、
- 仮説1.:一種の浮腫のような組織内で間質液がパンパンになって圧力が増しているのではないだろうか?
- 仮説2.:もしそうでなければ、姿勢動作に関係しない症状ということでレッドフラッグ(禁忌)にあたる可能性を検討。この場合は、腫瘍なども視野に入れて専門医に依頼を準備する
「2」のようなケースも過去、わたしを訪ねてきた患者の中にはいた。
その時は後から大腿の骨髄腫であったのが判明。油断は出来ない!
<実際のアプローチ>
触診では、しばらく積極的に安静にしてもらったにも関わらず、
やはり硬い弾力を飛んだままの三角筋であった。
小円筋
棘下筋
広背筋
肩甲下筋
菱形筋
前鋸筋
…の肩甲骨まわりの硬結や癒着がひどい。
上位胸椎や肋椎関節の可動域もかなり制限され背中が猫背気味…
そこでまずいきなり滑走の悪い癒着している組織間をリリースすることをせずに、
高周波治療器をかなり長い時間にわたってあてながらほぐしていった。
それからモビライゼーションテクニックやリリーステクニックを一通り肩甲骨まわりと肩甲上腕関節にまわりに施した。
大抵はそれで終わる、大抵は。
…
三角筋だけ張りが残っている(涙)。。。
<違う仮説> ~思考過程②~
もしかしたら「仮説2」か?
いや、待てよ…
局所循環の「供給(動脈系)」と「排出(静脈系/リンパ系)」とを考えたときに、浮腫のような表層ではない。
- 仮説3.けれど筋腹全体がパンパンだから、間質液で細胞間の圧力がかなり高い状態ではないか???
浮腫のような指を押しつけて跡がつくような感じではないけれど、
まだ他の可能性/仮説として、リンパ系による排出が制限されている…のではないだろうか?
でももう通常のリリースはかなり細かくそれぞれの局所局所の施術をしたけれど、足りないことは何だろうか・・・
そう、広範囲に皮膚全体をリリースできないだろうか!
<テーピングによる皮膚リリース>
そこで肩なのでゴムでグルグル巻きにしようとしても、
腕から脇あたりまでで肩全体まではカバーできないのでテーピングで覆ってしまうことにした。
わたしはスポーツのトレーナーでもあるので、テーピングは比較的簡単に肩全体を覆うことができた。
それから色々な方向に皮膚全体をずらしたり、
皮膚をずらしきったところでさらに動かしてもらったり
(希望者がいればいれば、セミナーを企画しましょう。希望者がいれば。)
・・・(テープを外す)・・・
見事、見た目も触った感じも通常の肩に戻りました!
レアなケースですが、「仮説3」の考え方が妥当だったようです。
お客さまもあまりの変化に涙して喜んでくれました。
めでたし、めでたし
…とはならずにこの話、さらに続きがあるんです。
それはまた次回に
理論先行型/テクニック先行型の治療家の先生へメッセージ
アンテナを張って、何かしらの兆候をこちらが感じ取れるかどうか、
またその通常とは違う目の前の変化や結果について「仕組み」や「原因」などを推察し続けること。
答えは1つではないからこそ、確認しつつ「トライ&エラー」を続けていけるか?
・・・
それが「結果の出せる治療家」に必須の資質です。
もう治療の勉強をはじめてから20年以上になりますが、
…まだまだ勉強です。
最後まで呼んでくれてありがとうございます。
PS:日本オランダ徒手療法協会では、オランダの理学療法士の技術や、リハビリの体系的な考え方、臨床で役に立つ情報をブログやセミナーを通して紹介しています。

特別割引です
膝を特集した【動画講座】で、初めての試みでオランダ徒手によるアプローチ全体の流れを包み隠さずに紹介しました!